この”もり”には
まだ きみの知らない「きみ」がいる。
scroll

きこえるかな?
ずっと むねのおくで なっていた その おと
それは ちいさくて
ことばには できないけれど
いつも そこに あった
この ものがたりは
その おとに ふれる たび
ひかりと かげと あなた自身が
やさしく とけていく
もう なにかを がんばらなくても いい
ただ 感じて
あなたの なかの 宇宙を
そっと ひらいてみて

amayえほん
-こんこんとしずかなもり-
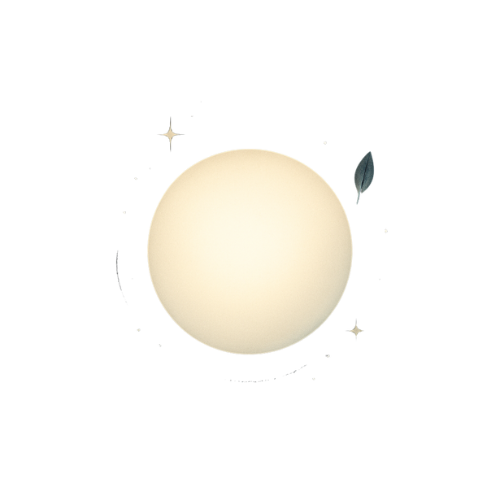

あるひ、ぼくは ふと きづいた。
なにも ないと おもっていた むねの なかに
ぽうっと ちいさな ひかりが
ただよっていた。
それは とても ちいさいのに
どこか なつかしくて、
なにより うつくしく
きらきら ひかっていた
まるで、
ずっとまえから そこに いたような、
ぼくの ことを ずっと まっていた
ほしのようだった。

その ひかりを そっと たどっていくと、
すこしずつ まわりの おとが しずかに
とおのいていった。
ぼくの なかが しんと しずまっていく。
なにも しゃべらなくても いいような、
ふかい やすらぎが ゆっくりと
ひろがっていく。
ふと あしもとに あらわれた
ひかりの みちを あるいていくと、
そのさきに——
すこしずつ まわりの おとが しずかに
とおのいていった。
ぼくの なかが しんと しずまっていく。
なにも しゃべらなくても いいような、
ふかい やすらぎが ゆっくりと
ひろがっていく。
ふと あしもとに あらわれた
ひかりの みちを あるいていくと、
そのさきに——

やさしくて やわらかい
ふしぎな もりが まっていた。
ふしぎな もりが まっていた。

もりの なかは、
しずかで、やわらかくて、
まるで だれかの
てのひらのうえに そっと
のせられているみたいだった。
すうっと いきをすると、
からだも おもいも
ふわっと かるくなっていく。
そこは、 なにも いわなくても
だいじょうぶな ばしょだった。
しずかで、やわらかくて、
まるで だれかの
てのひらのうえに そっと
のせられているみたいだった。
すうっと いきをすると、
からだも おもいも
ふわっと かるくなっていく。
そこは、 なにも いわなくても
だいじょうぶな ばしょだった。

もりの いちばん おくに、
ひとつだけ ぽつんと うかんでいる
ちいさな ひかりの たまが あった。
それは まるで ときを とめたみたいに
しずかに そこに ただよっていた。
ぼくは はなを すうっと すって、
こえを たてないように そっと
てを のばした。
ひとつだけ ぽつんと うかんでいる
ちいさな ひかりの たまが あった。
それは まるで ときを とめたみたいに
しずかに そこに ただよっていた。
ぼくは はなを すうっと すって、
こえを たてないように そっと
てを のばした。

その たまに そっと ふれた しゅんかん、
ぼくの むねの おくのほうに
ぽっ と あかりが ともった
からだのなかに やさしい ぬくもりが
ふわあっと ひろがって、
それは どこかで いちど
かんじたことのあるような、
とても なつかしい きもちだった。
なまえも ばしょも わからないけれど、
こころの いちばん ふかいところが
「しってるよ」って ささやいた。
ぼくの むねの おくのほうに
ぽっ と あかりが ともった
からだのなかに やさしい ぬくもりが
ふわあっと ひろがって、
それは どこかで いちど
かんじたことのあるような、
とても なつかしい きもちだった。
なまえも ばしょも わからないけれど、
こころの いちばん ふかいところが
「しってるよ」って ささやいた。

ぬくもりに ふれていると、
こころの いちばん ふかいところから
なにかが ゆっくりと
うかびあがってきた。
それは ことばにも ならないような、
かたちも ないような、
でも たしかに なつかしい きおくだった。
いつか どこかで、
たしかに かんじたことが ある——
そんな きもち。
こころの いちばん ふかいところから
なにかが ゆっくりと
うかびあがってきた。
それは ことばにも ならないような、
かたちも ないような、
でも たしかに なつかしい きおくだった。
いつか どこかで、
たしかに かんじたことが ある——
そんな きもち。

その あたたかさは、
ぬくもりだけじゃなくて、
なにか ぼくの たいせつなところを
そっと
なでてくれるような かんかくだった。
いっしゅんだけ、
なみだが でそうに なった。
だから ぼくは そっと なまえを つけた。
「こんこん」って。
よく わからないけど、
その こえが こころの なかで
ふと うまれた。
ぬくもりだけじゃなくて、
なにか ぼくの たいせつなところを
そっと
なでてくれるような かんかくだった。
いっしゅんだけ、
なみだが でそうに なった。
だから ぼくは そっと なまえを つけた。
「こんこん」って。
よく わからないけど、
その こえが こころの なかで
ふと うまれた。

「こんこん」は
なにも しゃべらなかった。
でも ぼくが そばに いると、
いつも すこしだけ
あかるく ひかっていた。
なにかを いわなくても、
なにを しなくても、
「だいじょうぶだよ」って
ずっと やさしく
みまもってくれている きがした。
なにも しゃべらなかった。
でも ぼくが そばに いると、
いつも すこしだけ
あかるく ひかっていた。
なにかを いわなくても、
なにを しなくても、
「だいじょうぶだよ」って
ずっと やさしく
みまもってくれている きがした。

あるひ きづいたら、
「こんこん」の ひかりが
しずかに ゆれていた。
いつもより すこし よわくて、
すこし ふるえている ように 感じた。
なにも いっていないのに、
なにか たいせつなものが
すこしだけ とおのいていくような
そんな きもちが した。
「こんこん」の ひかりが
しずかに ゆれていた。
いつもより すこし よわくて、
すこし ふるえている ように 感じた。
なにも いっていないのに、
なにか たいせつなものが
すこしだけ とおのいていくような
そんな きもちが した。

もりで すごす うちに、
ぼくの なかに ざわざわが うまれてきた。
なにが あったか おもいだせないけど
ふあんや さびしさが、
とつぜん おなかの そこから
のぼってくるような
そんな きもちに なることが ふえてきた。
なにを しても
うまくいかないような きもちも、
しらない あいだに まじっていた。
そして いつのまにか、
もりの くうきも
すこしずつ かわっていた。
まえより すこし おもたくて、
ひかりが うすくなった ような きがした。
ぼくの なかに ざわざわが うまれてきた。
なにが あったか おもいだせないけど
ふあんや さびしさが、
とつぜん おなかの そこから
のぼってくるような
そんな きもちに なることが ふえてきた。
なにを しても
うまくいかないような きもちも、
しらない あいだに まじっていた。
そして いつのまにか、
もりの くうきも
すこしずつ かわっていた。
まえより すこし おもたくて、
ひかりが うすくなった ような きがした。

ざわざわの きもちが、
まるで もりの くうきに
まざっていく みたいだった。
だんだんと ひかりは うすくなって、
しずかだった はずの もりが、
なにか かくしているように かんじた。
いきを するのも すこし たいへんで、
ぼくは ひとりで いることが、
すこし こわくなってきた。
まるで もりの くうきに
まざっていく みたいだった。
だんだんと ひかりは うすくなって、
しずかだった はずの もりが、
なにか かくしているように かんじた。
いきを するのも すこし たいへんで、
ぼくは ひとりで いることが、
すこし こわくなってきた。

あるとき
まわりの きりが すこしだけ こくなって、
その むこうに、
なにかが うごいているのが みえた。
くろくて、しずかで、
けむりの ようで、
でも そこに ちゃんと いた。
それは ぼくの ことを
まっすぐ みている ようだった。

さいしょは ただの
くろい かげにしか みえなかった。
でも そのとき、
とおくの とおくの ひかりが
まるで ぼくの むねに ことばを
おくってきたような きがした。
そのこえは きこえなかったけれど、
たしかに こころが うなずいた。
くろい かげにしか みえなかった。
でも そのとき、
とおくの とおくの ひかりが
まるで ぼくの むねに ことばを
おくってきたような きがした。
そのこえは きこえなかったけれど、
たしかに こころが うなずいた。

それが なんなのかは、
まだ よく わからなかった。
でも、
とおくで ひかっていた おおきな ひかりが
そっと おしえてくれた きがした。
だから ぼくは、
なんとなく——
「かげり」って よぶことにした。
まだ よく わからなかった。
でも、
とおくで ひかっていた おおきな ひかりが
そっと おしえてくれた きがした。
だから ぼくは、
なんとなく——
「かげり」って よぶことにした。

かげりは かたちを かえていった。
くろいもやのようだった そのすがたは、
だんだん おおきくなって、
とがって、ゆがんで、
こわい こえを だしそうな すがたに なった。
ほんとうは ちがうのかもしれないけど——
ぼくには そう みえた。
くろいもやのようだった そのすがたは、
だんだん おおきくなって、
とがって、ゆがんで、
こわい こえを だしそうな すがたに なった。
ほんとうは ちがうのかもしれないけど——
ぼくには そう みえた。

「かげり」は、
しずかに ぼくの まえに あらわれた。
こわい かおをして、
なにも いわないまま そこに たっていた。
そのすがたは おおきくて、
ぼくの こころに ぴたりと
ふたを したようだった。
まえに すすめない。
こえも でなかった。
しずかに ぼくの まえに あらわれた。
こわい かおをして、
なにも いわないまま そこに たっていた。
そのすがたは おおきくて、
ぼくの こころに ぴたりと
ふたを したようだった。
まえに すすめない。
こえも でなかった。

さいしょは、こわくて、ただ にげた
からだが ひとりでに うごいていた。
こわくて、
とまれなくて、
ぼくは ただ にげた。
からだが ひとりでに うごいていた。
こわくて、
とまれなくて、
ぼくは ただ にげた。

でも、まえにすすんでみたくて
なんども もりを でようとした。
でも そのたびに、
「かげり」は ぼくの まえに あらわれて、
なにも いわずに たちはだかった。
なんども もりを でようとした。
でも そのたびに、
「かげり」は ぼくの まえに あらわれて、
なにも いわずに たちはだかった。

がんばって あるいても、
すぐに かげりが でてきて
まえを ふさいでしまう。
もりから でたくても、
どうしても でられない。
かげりは いつも そこに いた。
すぐに かげりが でてきて
まえを ふさいでしまう。
もりから でたくても、
どうしても でられない。
かげりは いつも そこに いた。

なんども なんども、
ぼくは もりを ぬけようと した。
どうにか できるはずだと おもって、
くふうして、
ゆうきを だして、
あるいてみた。
でも、
なぜか そのたびに うまくいかない。
まえに すすめたようで、
きづけば また おなじ ばしょにもどっていた。
ぼくは もりを ぬけようと した。
どうにか できるはずだと おもって、
くふうして、
ゆうきを だして、
あるいてみた。
でも、
なぜか そのたびに うまくいかない。
まえに すすめたようで、
きづけば また おなじ ばしょにもどっていた。

どれだけ くりかえしても、
なにも かわらなかった。
こころも からだも くたくたで、
もう どうでも よくなってきた。
ぼくは そっと たちどまって、
もう あきらめちゃおうかな って、
こころのなかで つぶやいた。
なにも かわらなかった。
こころも からだも くたくたで、
もう どうでも よくなってきた。
ぼくは そっと たちどまって、
もう あきらめちゃおうかな って、
こころのなかで つぶやいた。

そのとき、
ふいに おもいだした。
もりに きた ときのこと。
「こんこん」に であってふれた
あの ひかりのこと。
いっしょにいるうちに きづいたら
その ひかりが ちいさく
ふるえていたこと。
ふいに おもいだした。
もりに きた ときのこと。
「こんこん」に であってふれた
あの ひかりのこと。
いっしょにいるうちに きづいたら
その ひかりが ちいさく
ふるえていたこと。

ずっとずっといっしょに いたのに、
ぼくは なにも きづかなかった。
こんこんの ひかりが
なにかを つたえようと してくれてたこと
ただ いっしょにいるのが
ここちよくて
ただ あんしんしていて、
その なかに まざっていた
かすかな ふるえを
ずっと みのがしていた。
ぼくは なにも きづかなかった。
こんこんの ひかりが
なにかを つたえようと してくれてたこと
ただ いっしょにいるのが
ここちよくて
ただ あんしんしていて、
その なかに まざっていた
かすかな ふるえを
ずっと みのがしていた。

だから、
ぼくは ——
こわかったけど、
どうしても しりたくて。
ぼくは ——
こわかったけど、
どうしても しりたくて。

かげりに
こわごわ ——
きいてみた。

「どうして ここに いるの?」
「なんで ぼくの じゃまを するの?」
「なんで ぼくの じゃまを するの?」

そのしゅんかん
とても しずかだったもりが
かすかに ふるえ
そのなかで、
かげりだけが うごかずに たっていた。
じかんという かんかくが ない じかん
むきあっていた。
きづくと はじめは
こわいと おもっていた かげりが、
とても しずかだったもりが
かすかに ふるえ
そのなかで、
かげりだけが うごかずに たっていた。
じかんという かんかくが ない じかん
むきあっていた。
きづくと はじめは
こわいと おもっていた かげりが、

みるみる ちいさくなっていった。
おおきくて こわかった すがたが
すうっと ちぢんで、
やわらかく ちぢんで、
まえよりも、
ずっと ちかくに みえるようになって——
ふと かおを みたとき
そこには、
どこか さみしそうな
かなしい かおが あった。
おおきくて こわかった すがたが
すうっと ちぢんで、
やわらかく ちぢんで、
まえよりも、
ずっと ちかくに みえるようになって——
ふと かおを みたとき
そこには、
どこか さみしそうな
かなしい かおが あった。

なにも いわなかった はずなのに——
こころのなかで こえが きこえた。
「まもってたんだよ、きみを」
その ことばが、
そっと ふるえるように しみこんできた。
そのとき——
こころのなかで こえが きこえた。
「まもってたんだよ、きみを」
その ことばが、
そっと ふるえるように しみこんできた。
そのとき——

なにかが すうっと ぬけていくような、
しずけさの なかで
かげりの おとのない こえで
ぼくは はじめて きづいた。
しずけさの なかで
かげりの おとのない こえで
ぼくは はじめて きづいた。

じゃまもの だって、
いやな そんざい だって、
ずっと おもっていた、
こわい もんすたー は——
いやな そんざい だって、
ずっと おもっていた、
こわい もんすたー は——

かげりは——
ぼくの こころが つくった、
ぼくを まもる ための すがただった
ぼくの こころが つくった、
ぼくを まもる ための すがただった

なみだが こぼれた。
「ありがとう」って いった。
いままで ずっと にげていたのに——
なみだが とまらなくなった。
「ありがとう」って いった。
いままで ずっと にげていたのに——
なみだが とまらなくなった。

「もう だいじょうぶ」って だきしめたら、
かげりは そっと、ひかりに なった。
かげりは そっと、ひかりに なった。

もりに、また ひかりが さしこんだ。
そっと、そっと、
かげりの のこした ひかりが
すみずみまで てらしながら。
そっと、そっと、
かげりの のこした ひかりが
すみずみまで てらしながら。
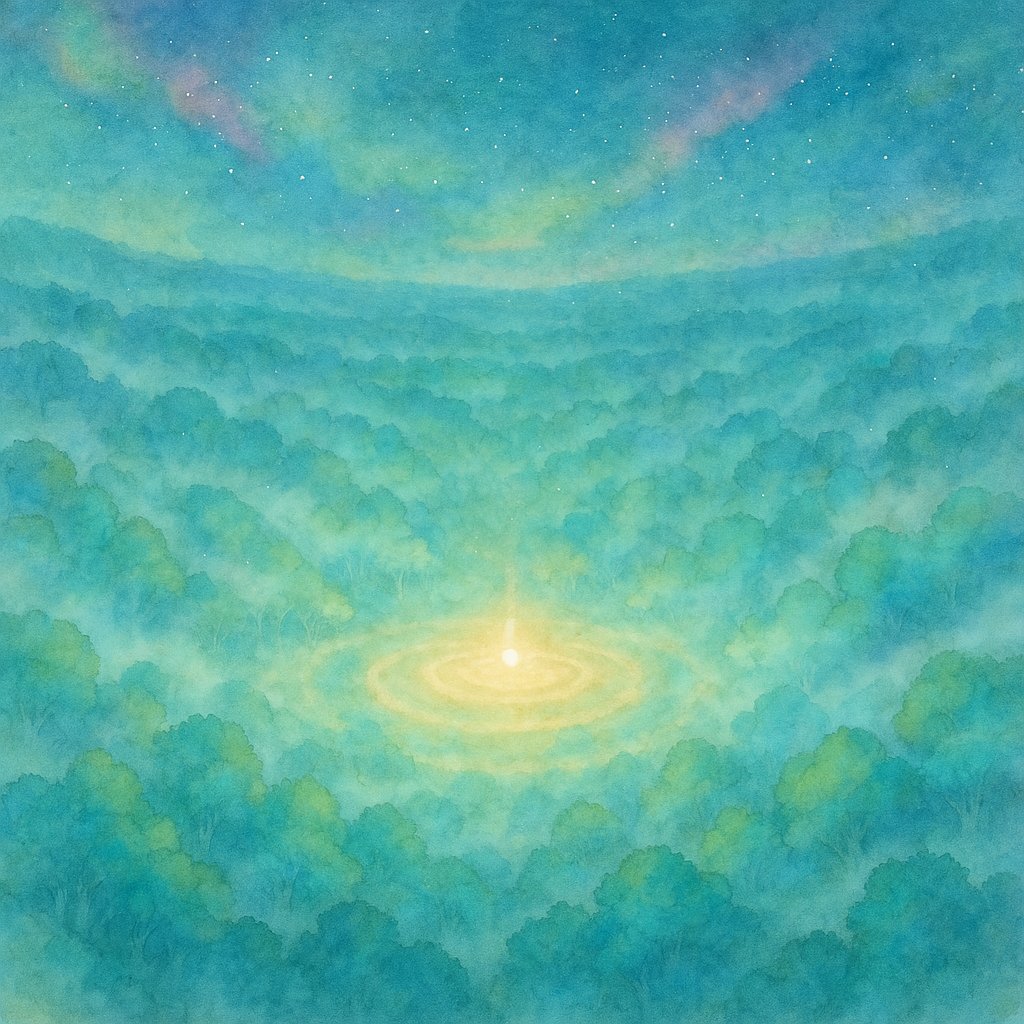
その ひかりと いっしょに
こんこん の ひかりが、
ゆっくりと ふくらんでいった。
それは あたたかな 風のように
ゆっくり、つよく、あたたかく
かがやき もりを てらした。
こんこん の ひかりが、
ゆっくりと ふくらんでいった。
それは あたたかな 風のように
ゆっくり、つよく、あたたかく
かがやき もりを てらした。

こんこんの ひかりが、
まっすぐに ぼくに とどいた きがした。
はじめて、
ほんとうの すがたに ふれたと わかった。
そのとき、
むねのなかが ぽっ、と あたたかくなった。
まっすぐに ぼくに とどいた きがした。
はじめて、
ほんとうの すがたに ふれたと わかった。
そのとき、
むねのなかが ぽっ、と あたたかくなった。

しずかな もりのなかで、
ぼくは もういちど、
「こんこん」に ふれてみた。
ことばも こえも いらなくて、
ただ そっと、 ふれた。
ぼくは もういちど、
「こんこん」に ふれてみた。
ことばも こえも いらなくて、
ただ そっと、 ふれた。

「こんこん」に ふれた そのしゅんかん——
ふわりと ひかりが あらわれた。
いろんな かたちの
”やっつの ひかり” が
ぼくのまえに そっと うかんできた。
ふわりと ひかりが あらわれた。
いろんな かたちの
”やっつの ひかり” が
ぼくのまえに そっと うかんできた。

たくさんの ひかりが うかんでいた。
そのなかで、
ひときわ つよく ひかる ひかりが あった。
すぐに わかった。
それが——
「ぼく」だった。
そのなかで、
ひときわ つよく ひかる ひかりが あった。
すぐに わかった。
それが——
「ぼく」だった。

そして ぼくは「ぼく」ときめたんだ
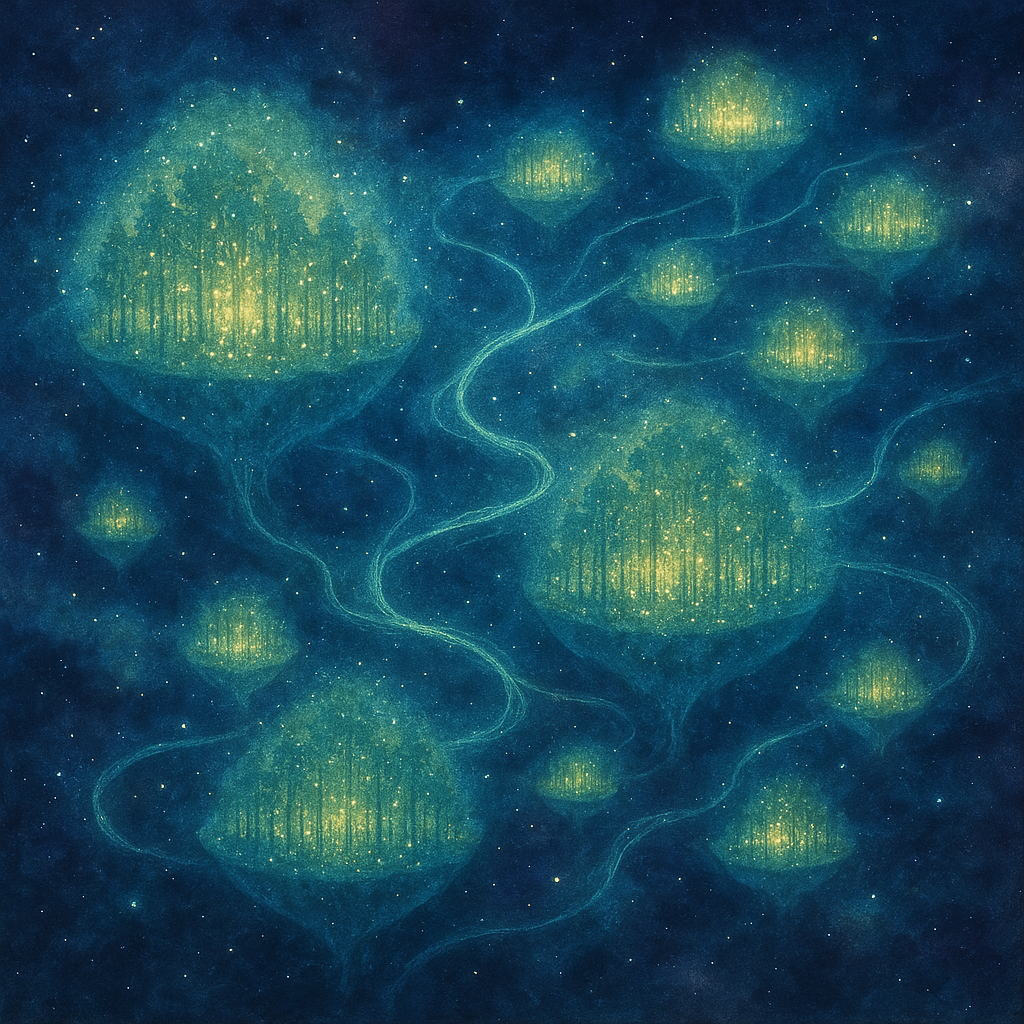
「ぼく」と いっしょに
だれかの もりに ひかりを
とどけるぼくに なるって。

そしたら なんだか
とおい とおい
あたたかい ひかりが
にっこり わらってくれた きがして
ぼくも わらった。
とおい とおい
あたたかい ひかりが
にっこり わらってくれた きがして
ぼくも わらった。
たくさんの ひとのもりに
あかるい ひかりが
とどきますように。
あかるい ひかりが
とどきますように。

-おしまい-
scroll
amayの森にふれてくれてありがとう。
もしよかったら、あなたの中にある
“ひかりのかたち”を、そっと見つけてみてください。
もしよかったら、あなたの中にある
“ひかりのかたち”を、そっと見つけてみてください。
▲
そっと ふれてみて
